バスは居るはずの無い魚か?
01/12/11
よく、バス駆除派が
「バスは居るはずの無い魚だ」
という表現を使います。
つまり、バサーや釣り業界の「闇放流」で広がったことを攻撃しているわけです。
しかし、それ以外にもバスが広がる要素がありました。
よく言われる、稚魚放流です。
以前、そのことを新聞投書や昨年のシンポジウムで話したのですが、
「混じらないように注意しているし、最近は人工孵化の稚魚なので、混じることは無い!」
と否定されてしまいましたが・・・
しかし、実際はそうではないようです。
1934(S9)年から1999(h11)年までの新潟県のアユの稚魚の放流実績が手元にあります。
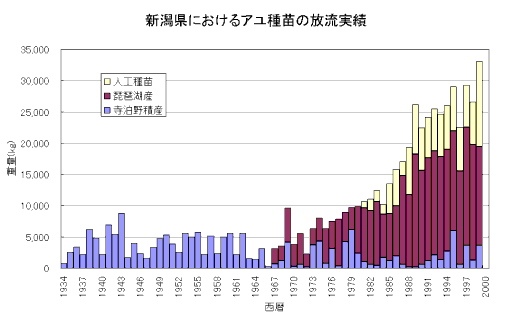
寺泊野積産というの信濃川大河津分水河口の野積地点の第二床固めという堰堤下で採捕されたアユの稚魚です。
信濃川では昭和6年に大河津分水の改修で堰堤が作られアユの稚魚が上りにくくなったのでこれを採捕して上流へ放流しています。
いわゆる天然のアユですね。
これを見るといろいろ興味深いですね。
戦前、少しづつ採捕量が増えていたのですが戦争でぐっと減ってしまいます。
その後、2500kg〜5000kgまで変動しながら横ばいで進みます。
この頃は環境も今より自然に近いでしょうからこのくらいがほぼ天然のキャパシティなのでしょう。
その後、60年代に向けてぐっと採捕量は落ちてきます。
この頃は高度経済成長で河川の環境が全国的に悪化してきたころだったからではないかと思います。
この後は途中、1981年、1982年頃大洪水があって一時的に採捕量が減ったりしつつも緩やかに回復しつつあるようです。
信濃川には1980年代後半にバスが入ってますがその影響は見られないようですね。
まあ、アユに対してはあるわけが無いのですが・・・
さて、問題は琵琶湖産アユですが新潟では高度成長で採捕量がへった60年代の終わりから放流が始まっています。
この少し後、1965年にブルーギルの生息が琵琶湖で確認されています。
そして、1974年にはラージマウスバスの生息が琵琶湖で確認されています・・・
この後もアユの放流は減るどころか増加の一方でした。
1983年に新潟県内で初めてバスが確認されてからも変わりません。
大体、現在では15〜18tほど新潟のあちこちに放流されてるわけです。
1匹あたり3gとすると5〜6百万匹になります。
ここからブラックバスの稚魚を区別しているのだから大変な苦労です・・・
人口種苗は1981年から始まってますがブラックバス混入対策ではなく、冷水病への対策です。
最近はアユだけでなく、ヤマメやイワナなど在来の多くの魚に感染しているそうです。
冷水病は琵琶湖産のアユに発生しやすいので問題になっていますが元はシルバーサーモンの病気です。
シルバーサーモンは日本には居ないはずなのですが・・・
という具合に、新潟県内のアユについて見ただけでもなかなかショッキングな事実が浮かんできます。
しかし、実際、現在のアユの需要を支えるためにはどうしても必要だったことですし、批判するつもりはありません。
とはいえ、バスはすべて違法放流で広がった、だから悪い魚だ!バサーはそれを支える悪い奴等だ!という短絡的な発想はこれを見ると滑稽なものに見えますね。