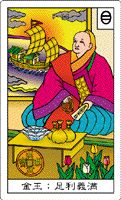
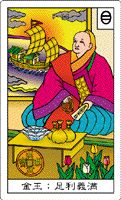
義満が大奥?へ触手をのばしていたのは後円融天皇は気付いていたらしい。しかし、怒りは義満にはぶつけることが出来ず、女性達にぶつけた。挙げ句の果てに自殺まで考えたらしい。治天の君である上皇がである。
とにかく、義満は天皇失墜のためにさまざまな画策を企んだ。そのためか、後円融は心労に耐えかねて若死にする(享年36歳)。後円融が若死にすると早速義満は次の仕事に取りかかる。
その仕事とは人事権の奪取である。武家の権力が頂点に達した江戸時代ですら、将軍という役職は天皇より宣化されるものだった。もちろんそれは形式的ではあるが、権限は権限で、力関係によってはどうなるか分からない。現に、幕末になったとき、朝廷の権威が復活し、将軍人事に朝廷が介入した。
後円融亡き後、義満は後継者の後小松がまだ若年(17才)なのをいいことに、人事権を天皇家から奪った。それを証明するには南北朝統一を述べなくてはならない。
南北朝統一は義満主導で行われた。その講和条件の中に、三種の神器は「譲国の儀式」をもって北朝の後小松天皇にあたえられる、と言うのがあった。「譲国の儀式」というのは、三種の神器を天皇から次の天皇に引き渡す正式な手続きのことだ。これを行う以上、渡す方の神器保有は正当なものと認められる。ということは、渡す側はちゃんとした手続きによって保管していたということになる。正当な所有者であったと言う証にもなる。
神器の正当な所有者、すなわち正当な天皇。この儀式を行う以上、北朝方も足利幕府方も、後醍醐ー後村上ー長慶ー後亀山という南朝の系譜および天皇をすべて正当なものと認めることである。
しかし、北朝側から見ると、これでは南朝が正統であって、その間、位に就いていた北朝の天皇はニセモノというハメになってしまう。
そこで北朝はあくまで「紛失していた」神器が戻ってきた、という態度にでた。これでは南朝側はおさまらない。それでは南朝がニセモノになってしまう。
義満は南朝側が怒って吉野に戻ってしまうとやっかいかと思い、尊号問題で南朝側よりの判定を下した。すなわち、後亀山は「不登極帝」(即位しなかった人の意味)であるが、現天皇の「父」に準ずるとして、強引に「上皇」の尊号を贈った。
「登極」というのは正式に天皇に即位することであり、北朝は、後亀山の尊号だけは何とか認めたが、「不登極帝」(帝をつけるのはまさか人とも言えないからで、苦肉の策だ)の例にならうと言うことは、やはり後亀山の天皇としての即位は認めず、当然治天の君(権力ある上皇)としても認めていないと言うことだ。
実は、誰を上皇と呼ぶか、と言うのは朝廷の人事権の最大のものの一つで、それを朝廷(北側)の反対を押し切って、後亀山上皇を実現させたという事は、義満が天皇に等しい人事権を掌握した事を意味する。
義満は後亀山上皇の件以外の点ではすべて南朝側との約束を反古とした。足利義満は南朝を一種の詐欺にかけて三種の神器を巻き上げることに成功した。しかし、このペテンによって、この国をまっぷたつにした大戦乱の原因が、見事に取り除かれた。これが政治というものだ。政治はマジック、小泉劇場がいい例だ??
05/9/27/12:55/
一つ指摘しておきたいけど(とはいえ、それは参考文献を読んでのことなんですが)、義満の天皇乗っ取り計画には、明らかに『源氏物語』の影響が見られることです。本来『源氏物語』とは光源氏という貴公子が、天皇の妻である女性と不倫に陥り子供を産ませ、その子供が天皇になって光源氏は准太上天皇になる、という出世物語。
臣下を准后(准三后)とするとは、皇族(太皇太后<たいこうたいごう>皇太后、皇后の三后)に準ずる扱い(准后=名誉皇族であり、あくまで人臣である。西洋では名誉白人というのがある)。
人臣と皇族では天と地の違いがある。天皇と皇族もそれぐらいの違いがある。人臣は太上天皇になれない。
天皇の妻たちと密通していた義満が、まさに「お手本」としていたのではないかと思われるほど、光源氏の生涯と義満の生涯には共通項がある。
初代尊氏、二代目義詮(よしあきら)あたりは戦争に忙しくて、『源氏物語』など読むヒマはなかっただろうが、義満は子供の頃から和漢の書物に親しんでいる。当然「源氏」も読んでいただろう。
そして、公家社会では「源氏」のことを知らない人間などいないから、義満がなにをもとめているのか、ということにはその時代暗黙の了解があったはずだ。
さて、義満は既に天皇家から、宮の人事権を奪い、上皇の「待遇」を得ていた。もちろん武士は大大名も含めて義満の完全な支配下にある。公家も僧侶(武家に劣らぬ権力者だ、だって、公家の口減らしでみんな僧侶になるのだから、まっとうな聖職者だなんて思ったら歴史が分からない。一休さんも義満の子供だぞ)も義満に逆らうものはすべて制圧され追放した。関白も義満に拝礼し、天皇すら義満の鼻息をうかがうしかない。その妻たちすらも「ねとられ」て、いたらしい。朝廷の後宮(大奥)は義満のハレムか!それじゃ後小松天皇も義満のこ×もか?
しかも、義満は対外的にはすでに「日本国王」であった。当時東アジア(とは、その当時の全世界の概念)の大国(明)から日本の王として認められていた(そうとうひんしゅくをかっていたが)。その地位を利用して貿易で莫大な利益を上げ、その財力でたとえば金閣寺のような豪華な建物を建てている。その中には目もくらむようなコレクションがあったとおもわれる。
天皇家が、現実の権力を失ってからも、権威を保ち続けられたのは、国の宗教を司(つかさど)る権利、つまり祭祀権(さいしけん)を持っていたからだが、義満はそれをも手中に収めたのだ。義満は、天皇家以外の人間で、もっとも限りなく「天皇」に肉薄した男である。万世一系の危機だ。
05/10/2/21:40/
義満は「天皇」になれなかった。天皇とは「血統」なのだ!!
義満は、その頃,、嫡男の義持(よしもち)とは不和だといわれている。溺愛していたのは、その弟の義嗣(よしつぐ)であった。義満は北山第(金閣)に後小松(むすこかもしれん)天皇を招いて義嗣が自分の後継者であることをしらしめた。そして義嗣は「親王」となった(本来、親王とは天皇の兄弟および皇子。のち、皇族で親王宣化を受けたものに限られた。集英社国語事典)。応永15年(1408)4月25日のことである。
非皇族の義嗣が立太子(りったいし)の礼で元服をしたのだ。のこるはただ最後の局面、後小松の禅譲(天子または支配者が自らの位を譲ること・ここでは後小松が義嗣に天皇位を譲ること)あるのみであった。しかし、天は義満親子に味方しなかった。親王元服わずか三日後、義満は不治の病で倒れた(病名は何だ?)。彼の遠大な簒奪計画は実現寸前で頓挫、夢と消えたのである。
もし息子義嗣が天皇になっていたら、義満は自ら太上天皇(上皇)となって、足利家を『天皇家』にするつもりだったのだろうか?
義満にとってはあまりにも不運である。しかし、同時に天皇家にとってみれば、望外の幸運。 \(^o^)/(万歳)を何度やってもやり過ぎたことにならないほどの「ラッキー」であった。
そこで、参考文献の著者である井沢元彦氏は、義満の死は自然死ではない「暗殺」ではないかとお考えだ。氏は、これまでにも学者とはひと味違う見解を提示され、さまざまな定説をくつがえしてこられた。では、やはり、義満の死は暗殺か?もしそうなら誰が義満を暗殺したか????
05/10/4/14:10/
ある人間が、政治でも戦争でも自分のやりたいことを成し遂げる機会に遭遇したとする。しかし、それはそのことを「成し遂げて欲しくない」人間にとっては最大の危機である。そういう危機を逃れるために、人間は、たとえ相手を殺してでも阻止しようとする。
「暗殺」と言う行為は、現代でもさまざまな国で行われている。暗殺が政治的な無差別テロと違うところは、政治的な重要な人物を殺すことによって、直接的な政治の方向性を変えようとする目的があることだ。
それゆえ、その人物を殺すことによって、確かに政治的な方向を変えられると言う確信がなければ、なかなか実行までには至らない。
義満の計画は達成寸前であり、しかも、義満以外に、これを実現できる人間はいない。義満さえ亡き者にしてしまえば、天皇家が乗っ取られると言う最悪の事態は確実に避けられる。関係者はそういう結果を容易に予測することが出来る。暗殺とはまさにこう言うときに起こるのである。(逆説の日本史7・<中世王権編>)。
それでは暗殺だったら、その犯人は誰か?それはもちろん朝廷側の人間だろう。武士階級も義満の計画には不満を抱いていた。息子の4代目の将軍の義持も、父のやり方には不満ではあった。
しかし、義持は朝廷側から義満への「太上天皇」の追贈(ついそう)を返上している。もし義持が義満暗殺にかかわっていたら、尊号宣化には反対しなかっただろう。なぜか?これは井沢元彦氏が常に言っておられるわが国独特の?「怨霊」というものがあるからだ。では、その「怨霊」と「義満尊号宣化返上」がどのような関わりを持つのだろうか。05/10/6/14:45/