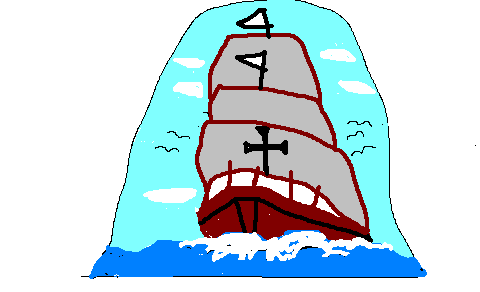
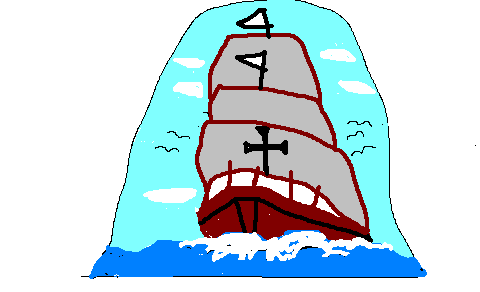
さて、ザビエルと同じポルトガルの宣教師ルイス・フロイス。彼の布教活動の1549年から1578年に至る布教編年史の中に、酒に関する興味深い記述がでてきます。まず日本酒の話しです。当時、すでに葡萄酒は外地から帆船に積み込まれて日本まで到来しているのに、日本酒は翌日になると酢になっていたと言うことです。室町時代、すでに上流階級では清酒らしきものも飲まれていたと言いますが、もちろん現在の清酒とは格段の違いがあります。まして一般には、酒は飲み物というより、朝鮮の「マッカリ」の様な食べ物で、すなわち粥状の酒に近かったと思われます。室町末期には、”かすみし空に似た「薄にごり」酒”が市場で立ち売りされていたと言われます。天平18年(1590)朝鮮の使節が来たとき、聚楽第で供応した酒も濁っており、土器(かわらけ)でその濁り酒を出したと朝鮮の柳成竜の「懲瑟録」に記録されています。これは身分の低いものが来たので、怒った秀吉が、酒も酒器もわざと粗略のものを用いたらしいのです。又、当時すでに日本の酒は温めて飲んでいたらしいのです。なにしろ酒は翌日までとっておくと酢になってしまうのです。そのためかどうかしれませんが、当時の日本では、清酒を蒸留した焼酎がつくられていたと思われるのです。
「焼酎・日本の酒の盲点」
広島県大口市の大口郡山八幡神社が昭和34年に改修された時、神社の屋根裏で木札が発見されました。言い伝えによると、この神社は700年前にたてられたものらしいのです。その木札には、永禄2歳8月11日と書かれています。永禄2年という年は、年表によれば西暦1559年、今から400年前に当たり、それは桶狭間の合戦の前年、中国では明の世宗の時代、西洋ではイギリスのエリザベス女王即位の翌年にあたる年です。そして、フランシスコ・ザビエルが鹿児島に来て我が国に初めてキリスト教を伝えたのは、この年より十年前、又ポルトガル船が種子島に漂着して鉄砲を伝えたのが十六年前のことです。さて、その木札には、その神社の建設に関係していた大工か、あるいは施主かが、棟札をあげるときに、日頃から吝嗇家の座主が、一度も焼酎をふるまわなかったことに対する鬱憤の言葉が書いてあるのです。このような時代に「焼酎」と呼ばれる酒が鹿児島県の一角に、しかも作事の際の大工などの飲み物として、すでに世間に広まっていたというのはオドロキである。ちなみに明の万歴年間に造られた李時珍の大著「本草綱目」(1578)は、それまでの中国の本草に関する文献を集大成したものであるが、それには「焼酒」という酒名があって、これは「火酒」及び「阿刺吉酒(アラキ)」の異名があることが記されているが「焼酎」と言う酒名がどこにも見あたらないから、少なくとも明の時代までは、中国では存在しなかった酒名であると見るのが妥当だと思われます。ところが、日本の江戸時代の正徳二年(1712)寺島良安によって著された「和漢三才図会」には見出しに「焼酒」とあり、それに「しやうちう」と仮名がついています。おそらく焼酎という言葉は「綱目」から「三才図会」に至る百三十年くらいの間に、日本か中国で作り出された言葉ではないかと思われます。要するに、その木札の発見により、「焼酎」と言う文字は、正徳2年(1712)に先立つこと百六十年も前に、鹿児島の田舎で、すでに一般に通用していたことが判明したのです。また、この木札は李時珍の「本草綱目」の書かれた年より20年も前に書かれたものであるから、少なくともその時代には焼酒にたいして焼酎と言う字は中国にはなかったが、日本ではごく普通に知られていたものと見られます。なお、泡盛についてですが、慶長13年(1608)島津家久の琉球征伐以来、泡盛が薩摩の独占輸入品となり、相当な量が薩摩へ輸入されるようになった。島津家では、これの一部を進上物として、幕府など要路へ贈られるならわしがあった。この泡盛は薬用が強調されており、また薩摩でも泡盛を造っていたが、その品質は劣っていた。それに濃度もうすかったようで、琉球の泡盛の足元にも及ばなかったようです。
「ポルトガルの日本来航はインドから」
16世紀の全般をほとんど毎年日本へ定期航海したポルトガル船の大部分は、彼らがナウと称する帆船でした。これについでは東洋のジャンク船が多く、終わりころにガレアンと呼ばれた種類の船もまれに来航している。ナウはイタリア語でカラツカと言い、英語でキャラックと称した(Carrack)。イスパニア船が日本に現れたのはこの世紀の終わりに近く、かつポルトガル船ほど頻繁ではなかった。ポルトガル、インド間では、これらの船が多いときは十数隻、少なくとも数隻の船隊をなして航海したが、当時日本へは通例一隻、ときにナウ一隻のほか、一、二隻のジャンクがきた程度です。それがインドのゴアを出向してマラッカ海峡を渡り、南シナ海を北上して遠路広東沖の上川島に達し、食糧を補給し、貨物を積んで台湾海峡を過ぎ、東シナ海を東に走って九州に達したのです。イギリスの商品はシナにおいて幾分売れるけれども、日本では中国からの生糸、絹織物であり、南方アジア地方の香木などで、決してヨーロッパからの商品ではなかったようです。これらのことが記述してある岡本良知著「16世紀日欧交通史の研究」によれば、ルイス・フロイス達が大村純忠に葡萄酒を贈った箇所があります。1536年1月14日に大村純忠はポルトガル人と会見し、いろいろな贈り物をされています。その中に葡萄酒があります。大村純忠はこの好意に対する答礼としてポルトガル人の船を訪れています。その後、ルイス・フロイスは二条状で信長と対面しています。信長はインド及びポルトガルの衣服その他の品を望んだ様ですが残念ながら南蛮酒の名はでてきません。イエズス会(耶蘇会)の宣教師ルイス・フロイス(1532〜97)が1585年6月、加津佐で書きしるした「日欧文化比較」には、「我々は葡萄酒を冷やす。日本では酒を飲むとき、ほとんど一年中いつもそれを温める。」、「我々の葡萄酒は葡萄の実からつくる。彼らのものはすべて米からつくる。」、「我々は片手で飲む。彼らはいつも両手を使って飲む。(しかし、女性は片手で盃を受けるのが礼であったようである)」、「我々が酒を飲むとき椅子に腰掛ける。彼らは跪く。」、「我々の間では銀製、ガラス製または陶器のコップで酒を飲む。日本人は木の盃または粘土の土器(かわらけ)で飲む。」、「我々の間では誰でも自分の欲する以上に酒を飲まず、人からしつこくすすめられることはない。日本では非常にしつこくすすめ合うので、ある物は嘔吐し、またあるものは酔っ払う。」これは400年近くたった今でも変わりませんね。「我々の間ではスープや魚の肉の椀で酒を飲むことは、吐気を催すほどいやなこととされているのに、日本では吸い物の椀で酒を飲むことが普通になっている。」、「我々の間では食事が始まるとすぐに酒を飲み始める。日本人はほとんどが食事が終わったころになって酒を飲み始める。」これは今の日本と違うようで、当時は饗膳の形式としては、食事のあと、酒宴となるのが普通だった。今の皇室ではどのように行われているのでしょうか。「我々の間では酒を飲んで前後不覚に陥ることは大きな恥辱であり、不名誉である。日本ではそれを誇りとして語る。」、確かに今でも酒量を誇る伝統はあるみたいですけど、記憶をなくすほど飲んだ次の日はいやなモンですけどね。また、ヨーロッパでは名誉ある市民が、居酒屋で売る酒を自分の家で売ることは卑しいことであるが、日本では大いに尊敬される市民が、それを売ったり自分の手で計ったりしていると記述してあります。室町時代以来、酒屋(酒造業)は土倉と並んで有力な商人の経営するところであり、そのことが宣教師達の目には奇異に映ったんでしょう。
「イエズス会士年報」による秀吉
1558年有馬発ルイス・フロイス「イエズス会士年報」によれば、豊臣秀吉が九州征伐ののち博多に立ち寄り、そこで耶蘇会士の乗っていたフスタ船(大砲を備えた船)を訪れて、糖果と、ポルトガル産の葡萄酒を喜んで賞味した旨がしるされています。またその年の5月14日、有馬で布教に当たっていた副官区長がルイス・フロイスその他の神父そしてポルトガル人の一行がキリシタン大名、小西行長の率いる水軍に伴われて秀吉と会談しました。秀吉は非常にご機嫌で、ポルトガル人の日本来航を歓迎し、その通商の自由を保障するとともに、ポルトガル船が大阪かその近くの港へ来るようにと希望さえしたと言います。ところで、この答礼と秀吉の戦勝を祝うために、当時平戸に居住していた副官区長クエリョは、秀吉が箱崎滞在中に博多へきた。沖合にポルトガル船がいたので、秀吉はこれに乗り移って船内を見学、船内では洋楽器が演奏され、クエリョのすすめた糖果とポルトガル産の葡萄酒を賞味し、長い間雑談したのちレモンの糖果漬けや葡萄酒を土産として持ち帰った。1594年(文禄三年)七月、フランシスコ派の宣教師、フライ・アウグスチン・ロドリゲスほか3名が日本に渡航するにあたって、フィリピン諸島長官は書簡を彼らに託して秀吉に届けることにした。一行は1594年八月下旬に平戸に着き、同九年末日、京都に到着。その時、書簡とともに秀吉に呈した進物の中に葡萄酒二樽とともにカバ一樽がある。カバ(CAVA)は当時のイスパニア、現在のスペインと国名が改められたが、この国の発泡酒スパークリングワインを言う場合の特別原産地の呼称である。「カバ」とはシャンパン西方でつくられるスペインの発泡性ワインで、約9割がペネデス地方で生産され、サン・サドルニ・グノイアはその中心地の観があります。400年前にこの発泡酒が秀吉に贈られていたということは、特筆に価しますが、当時すでにこの発泡酒がつくられていたという文献はまだ見つかっていないのだそうです。秀吉はその後、キリスト教弾圧に入ることになるのですが、彼とフィリピン間の貿易そのものをやめようとしたのではないのですが、その発端は、外国の日本への宗教進出があまりにも性急すぎたため、秀吉にとって、そうすることが最善であると考えたのも、当然ではないかと思われます。パート3に続く
 |
|---|
今から550年ぐらい前の室町中期に、すでに輸入酒が渡来していたと言うことが、伏見宮貞成(さだふさ)親王の書き残した、「看聞御記」に書かれています。この日記には室町最盛期の1416〜1448年の政治、社会の重要なことがらが書かれており、その中に舶来酒のことも書かれてています。そこには酒のことを唐物と書いてありますが、唐物(唐酒)とは必ずしも中国産を意味しないと思われます。当時は明の英宗の頃であって、かつて唐と言えば中国としていたが、この日記に記されている唐は舶来と理解してよく、舶来の酒、すなわち唐物のことなのです。そしてその酒は、甘くて黒い色をした酒だった。それでは甘くて黒い酒が当時東南アジアを含めてどこでつくられていたのか?中国の16世紀の書物「本草綱目」の蒸留酒の記述の項には、甘くて黒い酒のことを、焼酎をさらに復蒸したもので、産地はシャム(今のタイ)で、それは今日のジャマイカラムの強度にした様な物であるらしい。シャム酒は二度蒸留し、珍宝なる異香を入れる。その瓶は一個ずつ檀香十数斤を燃やした煙で薫じて、漆のようにし、その後、酒を入れて鑞で封をして土中に二年〜三年埋めて、焼気を絶去した後取り出して用いるらしいのです。しかし、シャム酒の原料はわからないようです。
さて、唐酒の記述があって、およそ30年の後に南蛮酒と言う舶来の酒がでてくる。それは京都の相国寺陰涼軒のあるじ達の公用日記「陰涼軒目録」文正元年(1466)の8月1日のところにでてきます。この南蛮酒は、のちアラキ、チンタとならび称され、チンタは珍陀の字を当て、赤い葡萄酒で、ポルトガル産の物です。この記述では、阿刺吉酒(アラキ酒)か珍陀か、いずれか明らかではありません。だだ、この酒は琉球国の正使が持ってきた物らしいのです。次に、カラサケと書いてある物もあります。応仁の乱の後、関白、太政大臣など枢要の地位にあった近衛政家のしるした「後法興院記」の文明15年(1483)4月16日のところにそれはでてきます。そこには、僧形をしたえらい人が、手土産に、折り箱が二個、カラサケ、金子などを持参している。唐酒をカラの酒と言っています。また、高麗酒という物もあります。「実隆公記」と名付けた三条西実隆(さねたか、1455〜1537)の日記にでてきます。高麗酒という物が、どんな物なのかわからないらしいが、当時の朝鮮でドブロクから蒸留酒が作られていたと思われます。また南方からいろんな物資が朝鮮へきていて、その中に焼酎もあって、この焼酎を日本では高麗酒と呼んだのかもしれません。ところで、15世紀の中国は明です。朝鮮は李氏朝鮮が成立します。日本の将軍は足利義満から義持に変わっていましたが、義満の舶来好きは相当なものでした。14世紀の中国の福健省の泉州は貿易の根拠地で、その商人は回教徒でしたが、圧迫されてジャワ、スマトラ、シャムなどへ移り、ここから南海地方の物産や、遠くペルシャ、インドの商品のみならず中国の物産をも交えてジャワ船、スマトラ船、シャム船などという南蛮船として、日本にも朝鮮にも売りに来たのでした。応永15年(1408)若狭の小浜にきた南蛮船は、スマトラのパレンバンの華僑のボス施進卿のもので、こうした中国の物産を含めた南蛮貿易は、主として、中国人(華僑)が掌握していました。そうした物資の中で、酒などはものの数ではなかったが、長い間の航海にも品質の変わらない、焼酒、阿刺吉酒(アラキ)、珍陀などが好適であったと思われます。
「ザビエル、マラッカから日本へ」
1549年(天文18年)7月、ポルトガルの宣教師、フランシスコ、デ、ザビエルは鹿児島に上陸し、島津貴久に謁見して、その地で伝導しました。ついで平戸を経て、山口で大内義隆に謁見しています。2年の後上洛しましたが、献上品を持っていかなかったために、将軍に拝謁を願い出たけれど許されず、とどまること11日で平戸に引き返しています。これにこりてか、山口へ再び布教に訪れたときは、インドの司教とインド総督の公式文書を携え、13の貴重な品々を大内義隆に贈っています。その贈り物の中には南蛮酒もあり、それはポルトガルの葡萄酒でした。フランスのワインが「ボルドー」「ブルゴーニュ」「シャンパーニュ」ドイツのワインが「ライン」「モーゼル」などの地理的名称を冠したように、ポートワインはポルトガルのオポルト港から積み出されるので、そういう名が付いたのです。ポルトガルという国名も、この「ポルト」からでたラテン名「ポルツカリア」から来ています。それから英語の「ポート」に転じたのです。
ところで、18世紀半ばの記録によれば、当時、西はブラジルから、東はマラッカにおよぶ多くの海外領地を持っていた大ポルトガル帝国は、ヨーロッパ諸国から船が集まってきました。そして、彼らはビィアナ港からテーブルワイン(甘くない食卓用葡萄酒)を、またリスボンから甘味デザートワインを買いつけていったと言うから、それがポートワインだからといって甘いとは限らなかったことになります。ボルドーやブルゴーニュの甘くない葡萄酒と同様のタイプのワインが、ポルトガルには当時から現代にいたるまで変わらず、甘いのと並立して作られており、どちらもがポルトガルのワインなのです。さて、別の記述によると、ポルトガル人自身は「ライトワイン」を飲用して、ポートワインは英国へ輸出するためにつくるものだとあります。ポートはブランデーを加えないでナチュラルワインに仕上げた場合、数年から十数年以内には飲用に適するようになり、15年も立てば最良状態に達するはずですが、英国人の嗜好に合わせるため、わざわざブランデーで強化するので、それ以上の貯蔵を重ねたりすることになるのだそうです。説明しますと、ポートワインはぶどうの糖分を大部分ワインの中に残さなければならないために、糖度計で計って最適の糖分を持つアルコール度に達したとき「ポルトガル産ブランデー(アルコール度数77%)」を加えて発酵を止めます。ポートワインが甘いのは、この天然の糖分のためなのです。なぜこんなタイプのワインをポルトガル人がつくったのでしょうか。当時、英国をはじめヨーロッパ各国へ樽詰めで盛んに輸出されていましたが、航海中のワインを健全に保っておくための処理として、このブランデー添付がなされました。1678年頃輸出業者はすでに少量のブランデーを加えたと信じられており、発酵中のぶどう果汁に加えるようになったのは18世紀半ばで、立法化されたのが1850年代でした。とすると、16世紀半ばに来航したザビエルが持ってきた葡萄酒が、ポルトガルの物に違いないが、甘味のある物かどうかは不明と言うことになります。 ところで、18世紀半ばの記録によると、当時、西はブラジルから東はマラッカにおよぶ多くの海外領地を持っていた大ポルトガル帝国へは、ヨーロッパ諸国から船が集まってきました。そして、彼らはビィアナ港からテーブルワイン(甘くない食卓用葡萄酒)を、またリスボンから甘味デザートワインを買いつけていったと言うから、それがポートワインだからといって甘いとは限らなかったことになります。
ポートワインとイギリスの結びつきは古く、17世紀まで遡るのです。1679年、イギリスは、敵対関係にあったフランスから一切の工業製品の輸入を禁止しました。これにともなって、イギリスのワイン需要のほとんどをまかなっていたボルドーワインもイギリスから姿を消すことになるのです。仕方なく、イギリスが目を付けたのが、ポルトガルのワインだったのです。当時のポートワインは、現在のようにフォーティファインド(酒精強壮)されたワインではなく、普通のテーブルワインでした。ポートワインの時代は1703年、イギリスがポルトガルとの間に、いわゆるメシェン条約を調印したこのによって始まったとするのが一般的な見解になっています。この条約の内容は、イギリスは、ポルトガルのワインをフランスのワインの3分の1という安い税率で輸入する変わりに、ポルトガルはイギリスの羊毛製品を買いつけるというものでした。しかし当時のポートワインは、クラレットを飲みつけたイギリス人にはとても口には合わず、このメシェン条約は、ポルトガルのワインへの嗜好を作りだしたと言うよりも、むしろフランスのワインへの思慕をさらに確認することになりました。と言うのは、ポルトガルでボルドーと同じようにワインをつくると、気候が熱いために発酵が早すぎて、ぶどうの糖分が全部アルコールに変化してしまい、粗く強いワインになってしまうのです。しかし、どうやら1720年頃には今日のワイン、つまり、フォーティーファインドされたポートワインの歴史が始まったようです。
さて、シェリーが最初に英国に輸入されたのは、16世紀の寒くて砂糖のない時代で(以前13世紀とかいた記憶があるが(^^;)ひとつの大きな贅沢品と言えるものでした。そうなると、ポートワインよりシェリーの方が先に作られていたことになるので、シェリーなら16世紀の日本へもたらされていたとしても納得できます。ザビエルの献上したポルトガルの葡萄酒は甘くなかったはずです。ション・セーリスの日記(慶長18年8月22日1613年)に、イスパニアの大使が駿府城で大御所様(徳川家康)に献上した品の中に「欧州の甘き葡萄酒五壺」の文字が現れるが、イスパニアの大使だあることから、このフォーティファインドワインはポートワインではなく、シェリーであったに違いないのです。
さて、平戸へいったん帰ってから後山口へ入ったザビエルは、インドの初代司教ドン・ファン・デ・アルブケルと、インド総督アルシア・デ・サが洋皮紙に書いた書簡各一通を添えて、十三の貴重な品を大内義隆に贈っていますが、これによってザビエルによるポートワインの伝来が明らかになりました。ザビエル以降の来航者が、日本の最高権力者として拝謁したり献上したりした相手は、天皇ではなく、関白であり将軍でした。「御門(ミカド)」「大君(タイクーン」などの尊称も、時の将軍を指したもので、朝廷とは全く没交渉なのです。ザビエルだけが、後奈良天皇を日本国王といい、都(京都)で天皇に拝謁を望んだということは特筆されてよいでしょう。献上品を持参してなかったのが謁見を許されなかった理由のようですが、当時の権力者は、献上品の値打ちによって伺候者の敬意の度合いを計ったとも考えられます。結局、葡萄酒をはじめ13種の品は、西日本で強い権力を持っていた山口の大内義隆に贈られました。パート2に続くトップに戻る