★正太郎BARうんちくコーナーにようこそ!
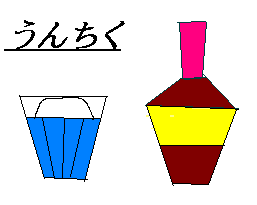 このコーナーでうんちく蓄え、BAR仲間に知ったかぶりして差をつけよう〜
このコーナーでうんちく蓄え、BAR仲間に知ったかぶりして差をつけよう〜
あの琥珀色と独特の香りで人気の高いウイスキー。じつは18世紀後半までは、色なし、香りなしのアルコール飲料であったとは、ちょっとオドロキ。ある時期をへて、同じ酒がこのように変身した原因は、やっぱり税金であった。18世紀のイギリスは、フランスとの7年戦争や、植民地だったアメリカの独立という二大アクシデントに見舞われ、政府の財政は大赤字。そこで考えつくのが、いつの世でも増税。てっとりばやく、酒税をなんと今までの15倍も引き上げた。そんなムチャな、とウイスキー業者も黙ってはいない。徹底抗戦とばかりにとった道は、人目に付かぬ山奥での密造であった。山のなかゆえ、蒸留する燃料は泥炭(ピート)、町まで運ぶ樽は買えないので、使い古しのシェリー樽で運んだ。町でこれを空けてみると、みなビックリ。無色透明なはずの液体が、香りはなんともいえず甘く、色は美しい琥珀色、味も今までとは雲泥の差の絶品もの。それもこれも、みんなもとはといえば税金と資金不足からの産物とは皮肉なもの。
以前、田中角栄さんが飲んでおられたことでも有名な、高級ウイスキーの代名詞でもあった(今はどうなんでしょうか?)オールド・パーは、スコットランドで実在していたトーマス・パーじいさんの長寿にあやかってつけたもの。1483年に生まれたこのおじいさん、なんと初婚は80歳の時。さらに105歳にして村の美女と不倫の恋に陥り、子供までつくってしまったが、妻を亡くしたあと、122歳で再婚。そして1635年、チャールズ1世に招かれてロンドンに赴いたのをきっかけに、酒池肉林の日々に突入する。153歳にして遂に天に召されたが、死因は食べ過ぎだったという、最後の最後まで元気なじいさんだった。私みたいに40過ぎたくらいでおジンだと思っている人間には信じられない人ですね。オールド・パーのラベルにはパーじいさんの肖像が描かれている。現在、パーじいさんはウエストミンスター寺院の墓地に、シェークスピアなどとともに安らかに眠っている。
バーの片隅の会話で”バルボン”と聞けば、昭和30年代には野球の阪急バルボン選手だった。私は小学生だったがバルボンは覚えている。少し色の黒い男の子がいて、彼は”バルボン”と呼ばれていて、なるほでなアと感心していたものだ。実はこのコーナーを書こうとしていたら偶然に、北日本新聞の夕刊にお菓子の”ブルボン”の社名のことについて書いてあった。そこには・・・・社長がたしかに付けた名前だが、由来は「フランスのブルボン王朝をイメージしたのでは」との声もあるが、同社は「前社長が昨年急逝したため、何故そうなったのかわからない。」とのことであった。そんなわけで、昔はバーボンという言葉は野球選手かお菓子の名前としての方が浸透していたわけである。(ちなみにバーボン=ブルボンと思って下さい)さて、現在のようにバーボンが酒場に当たり前のようにおいてあるようになったのは、ほんの10年くらい前からだとおもいます(都会はもっと早いかなぁ)。私が20代だった昭和40年代から50年代の主流のウイスキーはブレンディドのホースやカティーサーク、バランタインなどであった(若者はもっぱらホワイトか黒の50、バーボンを飲む人は臭い酒を飲む変わり者と呼ばれた)。もっとも、本国アメリカでも、”bourbon"とその名をラベルに刻んで登場したのは、ほんの1世紀半ほど前にすぎない。それまでは、レッド・リカー(赤い酒)とか、リクィッド・ルビー(ルビー色の液体)とか、レッド・クリーチャー(赤い生き物)などと、もっぱらその明るいゴールデン・ブラウンに輝く色彩をたたえて呼ばれていたのだ。ちなみに、バーボンよりもウオッカの方がよく売れると言われていたのだが、現在もやっぱりウオッカの方が売れているのでしょうか。
あのマリー・アントワネットが、またナポレオンがこよなく愛した、琥珀色の栄華のお酒、ブランデー。だがこの格調高いお酒の誕生は、その名声ほど華やかなものではなかった。時は17世紀後半、フランスコニャック地方のワインは、オランダ貿易商によってイギリスなどに取り引きされていた。珍しさも手伝って、少し売れはしたのでが、ボルドー産の人気に今一つ勝てず、蔵のワインはたまる一方。頭を痛めたワイン業者達、ならいっそ蒸留してみましょうと言うことで、出来たお酒がブランデー。色といい、まろやかな香りといい、気品があってすばらしい。これはイケそうというので、ブランデーづくりが広まったそうだ。コニャック地方のワインが超一流だったなら、ブランデーも生まれず、ベルサイユ宮殿のあの華やかさも、チョットは別のものになっていたかもしれないですよね。
アメリカ映画などで見るワンショット・バーには、日本のバーのような椅子がない。客は立ったままカウンター下の棒に片足をのせて、ウイスキーをグィッとあおる。まことにイキである。ところで、日本のバーの草分けといえば、明治はじめに銀座でオープンした「函館屋」である。カウンターだけのスタンド式で、左右に洋酒の瓶が並ぶ高級な店であったとされている。口ひげ、洋装のハイカラ紳士が表にお抱え運転手を待たせて飲んだというからそうとうのもの。いっぽう、浅草の「神谷バー」も、日本のバーの第1号として知られているが、こちらは居酒屋ふうでグッと庶民的。因みに私の知っている戦前からのお店で「サンスーシ」がある。このお店もスタンドバーであったが、私が訪ねた10年ほど前はすでに椅子がおいてあった。バーの世界では神様とも言われるクールのマスターはこのお店の出身である。
ラムといえば、灼熱の太陽のカリブ海の酒。西インド諸島周辺では、酒と言えばラムをおいて他にない。ラムベースのカクテル”ダイキリ”などは、ハバナ時代のヘミングウェイが飲んで世界的に有名になったし、フロリダあたりでも人気があるのはもっぱらラム・ベースのカクテルらしい。そもそもラムの原料は西インド諸島産のさとうきび。16世紀初頭にやってきたスペイン人がきびの糖蜜を発酵させ、蒸留してつくったのがはじまりといわれる。やがてスペイン無敵艦隊をドレイク率いる英国海軍が破り、ラムを発見。ラムという名は、イギリスの方言で乱痴気騒ぎ”ランバリオン”という語からきた、というのが定説である。一方英国海軍の酒好き提督”オールド・ラミー(飲んだくれおやじ)からきたなどという説も飛び交っている。
外国人船員の常連の多い港町のバーに行った人が、気取ってギムレットをたのんだ。30分もかけてちびちびなめていたら、半分残っているにもかかわらず、白人のウエイターの凄腕がのびてきて、そのままかたづけてしまった。なんて失敬な・・・と思う前に、酒を愛する皆さんならここで怒ってはけない。カクテルの別名ともいえるロングドリンクスとショートドリンクス。ロングドリンクスは、ただ背の高いトール・グラスに入ってでてくるものと思いきや、実は30分おきざらしにしておいても、味は変わりにくいもの。いっぽう、早くのみほしてこそおいしいのが、ショートドリンクス。ギムレットはもちろん後者である。それさえ知っていれば、言葉の通じないウェイターのこころづかいに軽くほほえむこともできるというものだ。
18世紀後半頃まで、ワインは昔の日本酒と同様、木樽からそそぐのが普通だった。瓶ずめワインの歴史は、以外と浅いのである。瓶に詰めたワインは、樽に入れておくよりはるかに保存がきくが、こまったことに、コルクがかわくとすき間が出来て、外部からの空気が入り込んでしまう。空気に触れるとワインが酸化するのは周知の通り。そこで寝かせておいて酸素の出入りする量を減らそうと言うことになったのである。コルクに常に湿り気を与えておけば、出入りする酸素量は立たせておくときの30分の1に減るとか。よりうまいワインを飲むための、ひとつの知恵である。
へべれけによって最終電車に乗り遅れた、という人もいるだろう。この「へべれけ」の語源が面白い。日本語ではなく、ギリシア語の「ヘーベーリュエケ」に由来する。「へーべーのお酌」という意味らしい。「へーべー」とは神話の男神ゼウスと女神ヘーラーのあいだに生まれた女神である。へーべーはオリンピアで酒宴が催されると、お酌をして回るのが役目だった。酒席の男神たちは美しい女神のお酌で「へーべれけ」に酔ったと伝えられる。もう一つ、酔っ払いのことを「トラ」ともいいます。飲み過ぎると、トラのように凶暴になるからだ、と思っている人も多いが(実は私も)、そうではなく、昔は酒を「竹葉(ちゅくよう)」といい、女性は「ささ」と呼んだ。トラは竹やぶにすんでいるので、酔っ払うことを「トラになる」と言うようになったそうです。くれぐれも飲みすぎには注意しましょうね、正太郎さんもネ。
よく、酔っ払いが愚にもつかぬ事をしつこく話しているのを「くだをまく」という。このくだとはなんだろう。広辞苑によれば、「管(くだ)」とは機織りの道具で、糸繰車を巻き付ける小さな軸を指す。この管が回転するときにブウブウという音を立てるのだそうだ。また、管を巻く作業は、呼び名の通り大変にくだくだしい作業である。酔っぱらいの話もまた、ブウブウという音に近く、しつこくてくだくだしい。そこで、酔っ払いのたわごとを、「くだをまく」というようになったのです。こんな酔っ払いの人に出くわしたときは、感心しながら聞いているフリをして、さりげなく席を外すのがいいそうです。私はひょっとしたら、はずされるほうかもしれない、気をつけなくては・・・・・。
関西の落語を「上方落語」などと称するように、関西地方のことを「上方」というのは、明治維新で東京が首都になってからも変わらない。特に酒の世界では、灘や伏見の酒を”上方酒”とよんで、おおいに愛(め)でてきたのである。江戸時代、この”上方酒”は二とう樽に入れられ、馬にくくりつけて東海道を江戸に下った。しだいに馬から船にと運送手段は変わりはしたが、いずれの手段によろうとも、これらの酒はすべて”くだり酒”とよばれた。当時の酒樽は吉野杉で作られたものが最上とされ、それが東海道をゆられるあいだに、木の香りが酒に移り、江戸で賞味するころがちょうど結構な味となるところから、”下り酒”の人気はいやが上にもあがっていった。”下り酒”に比べて、関東周辺の酒は「地回り」とよばれ、東海道を下ってこない酒、つまり「くだらない酒」はうまくない、という評判がいつしか定着してしまった。この評判がいつしか、つまらないことや内容のないことを、「くだらねえ!」と表現するようになり、江戸の新造語となったという。しかし、以上は江戸時代のお話、現在は茨城、栃木、千葉(五人娘を最近飲みました)そのほかの「地回り」の酒も東海道をくだりはしませんが”上方酒”に決してひけをとりません。
スクリュー・ドライバーやブラディ・マリーのベースとして有名なウオッカ。このウオッカの生まれは、もちろんロシアである。13世紀から16世紀、モスクワ公国時代には、高貴なスピリッツとして好まれ、皇帝や貴族に、そしてそれ以後は国民にも盛んに飲まれたが、欧米各国との外交も少なかったため、世界に広がることはなかった。このウオッカのうまさが世界に知れわたるきっかけとなったのは、1917年の3月、および11月の二度にわたるロシア革命によってであった。そのウオッカの名は「スミノフ」。1818年、ピエール、スミノフが発表したのが始まりだが、ロシア革命により、子孫のウロジミール・スミノフはその時パリに亡命。小工場で、亡命ロシア人のためにウオッカをつくるようになった。これが西欧でもウオッカが知られる第一頁になった。
元に戻る
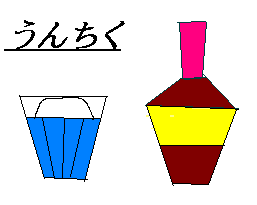 このコーナーでうんちく蓄え、BAR仲間に知ったかぶりして差をつけよう〜
このコーナーでうんちく蓄え、BAR仲間に知ったかぶりして差をつけよう〜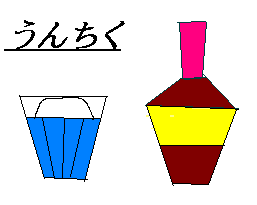 このコーナーでうんちく蓄え、BAR仲間に知ったかぶりして差をつけよう〜
このコーナーでうんちく蓄え、BAR仲間に知ったかぶりして差をつけよう〜