Ⅰ 落差工の騒音対策の必要性
近年、農業用用排水施設周辺の宅地化が進み、維持管理や安全対策等、種々の問題が生じているが、開水路の勾配調整の為に築造されている落差工の落下水音による騒音問題もその1つとなっている。土地改良事業設計基準 「水路工」でも、「市街地及びその周辺で落差工を計画する場合は、騒音、振動、飛沫等の対策を検討しなければならない」としている。
Ⅱ 騒音対策を必要とする落差工
落差工の種類としては、落ち口直下が鉛
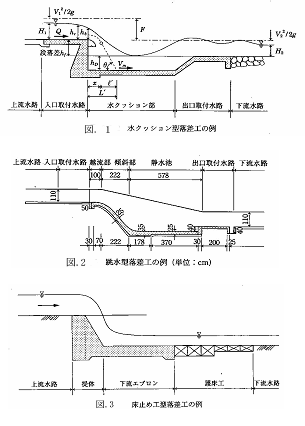 直段落となっており、減勢のための水クッションを有する水クッション型落差工(図.1)と、落ち口が傾斜段落となり傾斜面にそって静水池に導かれる跳水型落差工(図.2)、及び落ち口から急傾斜段落となり、流水が下流水叩きに衝突して減勢される形式の床止め工型落差工(図.3)等がある。用水路や小規模な排水路では構造が簡単で施設規模が小さくなる水クッション型落差工が多く採用されており、河川等では床止め工型落差工が採用されている。
直段落となっており、減勢のための水クッションを有する水クッション型落差工(図.1)と、落ち口が傾斜段落となり傾斜面にそって静水池に導かれる跳水型落差工(図.2)、及び落ち口から急傾斜段落となり、流水が下流水叩きに衝突して減勢される形式の床止め工型落差工(図.3)等がある。用水路や小規模な排水路では構造が簡単で施設規模が小さくなる水クッション型落差工が多く採用されており、河川等では床止め工型落差工が採用されている。このうち、最も騒音対策が必要とされるのは、水クッション型落差工であり、跳水型落差工については落下水脈が斜面に沿って静水池に流れ込むため、水クッション型落差工に比べ、静水池の衝撃音が少ないとされている。床止め工型落差工は騒音に関しては両者の中間に位置するが、住宅地に近接されて設置されるケースは比較的少ないと思われる。
Ⅲ 水クッション型落差工騒音対策の方針
水クッション型
 落差工は水脈が水クッション部に突入する際に生ずる衝撃や水中噴流の拡散によって落下エネルギーを吸収し減勢を行うもので(図.4)、この時の衝撃音と水クッション内に連行された空気の消散音等が騒音の原因になると考えられる。このうち人に不快な騒音と認識される主なものは衝撃音であり、この衝撃音を低減することが騒音対策に最も有効な方法であると考える。
落差工は水脈が水クッション部に突入する際に生ずる衝撃や水中噴流の拡散によって落下エネルギーを吸収し減勢を行うもので(図.4)、この時の衝撃音と水クッション内に連行された空気の消散音等が騒音の原因になると考えられる。このうち人に不快な騒音と認識される主なものは衝撃音であり、この衝撃音を低減することが騒音対策に最も有効な方法であると考える。
Ⅳ 騒音対策の現状
新規に落差工を計画する場合は、住宅地に隣接した位置を避けたり、勾配調整による落差の低減、跳水型落差工の採用等で騒音問題を回避する事が可能であるが、既設の落差工の騒音対策には苦慮している事例が多いように思われる。
現状で行われている対策としては、防音壁及び防音蓋の設置、跳水型落差工への改造などがあるが、防音壁及び防音蓋の設置は一定の方向には有効であっても、他方向にはかえって大きな音を発生させるとの実験報告もある。(農土試技報B水理51号)、また、跳水型落差工への改造は多額の工事費がかかることが問題となる。
Ⅴ 騒音低減施設の提案
1. 水クッション部背面壁が利用出来る場合
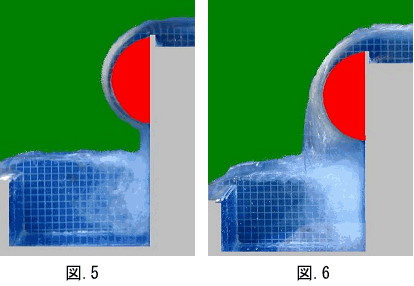 ここに提案する騒音低減施設は、水クッション型落差工における落下水脈を、落ち口直下流に設けた半円体によって水クッション部背面壁に衝突させ、落下水のエネルギーを吸収し水面への衝撃音を低減する事を目的としたものである(図.5)。この場合、流量が設計流量より増加すると水脈は半円体から剥離するが、直接落下する場合に比べ、流速が減少しており、落下幅も大きくなるため、水面への衝撃音も少なくなると予想される(図.6)。
ここに提案する騒音低減施設は、水クッション型落差工における落下水脈を、落ち口直下流に設けた半円体によって水クッション部背面壁に衝突させ、落下水のエネルギーを吸収し水面への衝撃音を低減する事を目的としたものである(図.5)。この場合、流量が設計流量より増加すると水脈は半円体から剥離するが、直接落下する場合に比べ、流速が減少しており、落下幅も大きくなるため、水面への衝撃音も少なくなると予想される(図.6)。2. 水クッション部背面壁が利用出来ない場合
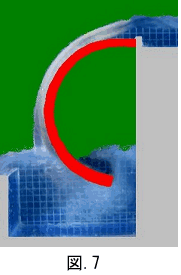 流量により決まる半円体の大きさに対して落差が少ない時、上記の効果を期待することが出来ないが、図.7のような形で半円体を設置すれば、落下水脈は高速で水クッションに突入し、水勢は半円体の円周方向に進んで、その内空部に噴出するため、発生する水音は跳水型落差工程度となり、直接落下する場合に比べ衝撃音はかなり軽減されるものと考える
。
流量により決まる半円体の大きさに対して落差が少ない時、上記の効果を期待することが出来ないが、図.7のような形で半円体を設置すれば、落下水脈は高速で水クッションに突入し、水勢は半円体の円周方向に進んで、その内空部に噴出するため、発生する水音は跳水型落差工程度となり、直接落下する場合に比べ衝撃音はかなり軽減されるものと考える
。3. 落差が大きい場合
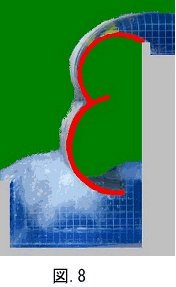 落差が特に大きい場合、上記1の例では背面壁に当たった水脈が再度加速されて水面に落下する事になり、衝撃音の低減効果が減少する。また、上記2の場合は施設規模が大きくなり、価格面での問題等が生ずる。このため、図.8のような2連の半円体の組合せを行えば、大きな落差への対応が可能と考えられる
落差が特に大きい場合、上記1の例では背面壁に当たった水脈が再度加速されて水面に落下する事になり、衝撃音の低減効果が減少する。また、上記2の場合は施設規模が大きくなり、価格面での問題等が生ずる。このため、図.8のような2連の半円体の組合せを行えば、大きな落差への対応が可能と考えられるⅥ 他工種への適用
ここに提案した施設は水クッション型落差工を対象としたものではあるが、床止め工型落差工はもちろん、オープン型パイプラインの水位調整施設であるチェック工にも適用可能である。小規模なパイプラインシステムではフロートバルブ等で水位制御される場合が多いが、大口径の場合、越流堰でチェック水位を保つタイプとなり、堰からの越流落下水の発生する騒音が問題となる時がある。このようなチェック工の越流水深は0.30mから0.50m程度で、m当たり流量は少ないため、比較的小規模な半円体で対応出来るものと予想される。
Ⅶ 実用化への課題
ここでの提案は簡易な水理実験によって得られた視覚的なデータと、落差工の騒音問題に対する一般論的な把握によるものであるため、実用化に当たっては、下記の課題への対処が必要である。
1. 騒音低減効果の定量的な把握
施設を設けない場合の騒音が、施設を設けた事によりどれだけ減少されるかを数値(dB)で把握する
2. 半円体から水脈が剥離しない流量の把握
水流が半円体の円周方向に流れる現象は半円体表面の摩擦抵抗と水の粘性によるものと思われる。このため、ある半径に対して水脈が剥離しない流量は半円体の表面粗度が一定であれば、一定値に決定される。各半径ごとに対応できる流量を実験的に決定すれば、設計流量に対しての半円体の選定が可能になる。
3. コスト縮減効果の検討
公共工事として採用されるためには、現行の対策工法に対し、その効果が確実であることに加え、コスト縮減の効果が無ければならない。このため、一般に行われる工法(たとえば跳水型落差工への改造等)に比べ、安価な価格で製作据付の出来る材質・工法の検討が必要である。
以上のように考察しましたが
| 実験をしてみたところ ここに提案した半円体を使用するほうが、自由落下の場合に比べ 騒音が大きくなる ことが判明しました。 |